う~~~ん、「【和訳に挑戦!】Economic Gardening」は、他人様から
ナ~ンダ、と思われてしまいそうですが、2回で断念か・・・・・〇| ̄|_
日曜夜12時まで。そして、火曜午前0時から。月曜日というのは、私に
とって比較的、時間に余裕のある一日。もっとも近頃は、寒さが加わって、
どうしても“寝貯め(冬眠?)”する一日と化しているような・・・・。
外へ出るのも億劫だ・・・と思っていたら、「そうだ!勤め先で使う、
キッチンペーパーを買っておきゃなきゃいけなかった!!」。
(フライドポテト・フライドチキン等々、揚げ物を大量に揚げてりゃあ、
それだけキッチンペーパーを消費するわけで)
あわてて、髭も剃っていない状態で、だいわへと。

とはいえ、和訳に挫折しつつあれば、日本語の本を読み出す・・・。
さて、8冊の中から、どういう順番で読み出そうか迷ったのですが、
まず手にしたのは、こちら。
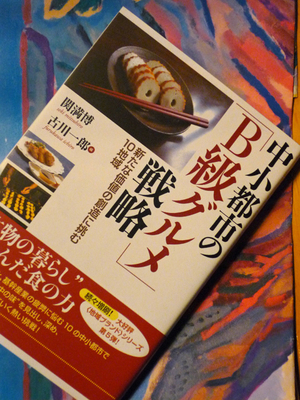
『中小都市の「B級グルメ」戦略―新たな価値の創造に挑む10地域』
関満博&古川一郎編、新評論刊、2,625円
(Amazonの紹介ページ⇒こちら)
比較的読みやすいものから手にして、エイヤッ!と勢いをつけて、
難解そうな本に挑戦する戦法。
とりあえず、序章・終章を含めて全12章で構成されるうち、第8章
まで拝読。やっぱり「食は、胃袋のみならず、心も満たす」、オッホ
ン・・・。読中、ああ食べに行きたいな~~、と普段外食なぞしない
私でも、思うもの。
ご当地グルメは、その地域の文化である。
その観点からすると、「B級グルメでまちおこし」は、とっても
正攻法の地域振興策であるな~~と、再認識。
とはいえ、
「第六章 須坂みそ料理/伝統的な地域資源を生かす」
で、ハタと読むの、停止。。
長野県須坂市、人口五万三〇〇〇人、
『・・・・
さらに、第二次大戦後は富士通が須坂市に工場を建設したことで、
企業城下町として繁栄した。しかし、一九九六年バブル経済崩壊のあお
りを受け、富士通は須坂工場の縮小を決定し、六〇〇人以上の人員削減
を行った。 ・・・・・』
現状の出水市に相通じるものがある?
またまた、patmap都市情報のお世話になります。(須坂市の項⇒こちら)
出水市と主な部分を比較してみます。
須坂市 出水市
人口総数(2005) 53,668[人] 57,907[人]
(可住地面積に対する)
人口密度 1074.65[人/k㎡〕 496.29[人/k㎡]
県都・長野市に隣接するだけあって、恐らく須坂市の方が“都会”(笑)
というイメージが強いのでしょうね。
次に、産業別従業者数で比べてみると、
労働力人口 29295[人] 29634[人]
就業者数 27959[人] 27823[人]
第1次産業就業者数 3678[人] 4596[人]
(13.2%) (16.5%)
第2次産業就業者数 9245[人] 7724[人]
(33.1%) (27.8%)
第3次産業就業者数 14985[人] 15488[人]
(53.7%) (55.7%)
さらに、農業生産額と工業・製造品出荷額等を。
農業産出額(2006) 593[千万円] 2,419[千万円]
製造品出荷額等 125,737[百万円] 110,007[百万円]
粗付加価値額 54,947[百万円] 41,299[百万円]
現金給与総額 25,281[百万円] 15,863[百万円]
須坂市は、長野市のベットタウンという側面もありつつも、出水市
と比べれば、はるかに「工業都市」であるようですね。
最後に、もっといやらしく、pitmap都市情報に掲載されていない、
「市民一人あたりの分配所得」も、ガサゴソと該当自治体サイトを探し
ながら・・・、
須坂市 出水市
平成17年度 2,703千円 2,106千円
・・・・でも、これって、我らが鹿児島県・“花の都”鹿児島市であって
も、「2,558千円」であるのだとか。ちょっと打ちのめされた感じ・・・。
「まちおこし」では語れない、「グルメ番組」では見ることができない、
日々の地域の経済活動、そして、そこに暮らし人々の普段の生活から、
何を読み取り、地域政策を形にするか・・・・・・。
って、とっても地味でしょうが、でも必要である、と。
本の内容から大きく逸脱してしまいましたが、
いやいや、ですから、「ご当地グルメ」といえば、私のような“部外者”
でも、ワイワイガヤガヤ意見を出せるわけであり、“勝手に宣伝隊”を自
称できるはずであり・・・。そんな「楽しさ」を、否定するつもりはあり
ません。
とりあえず、終章まで読み通してみます。









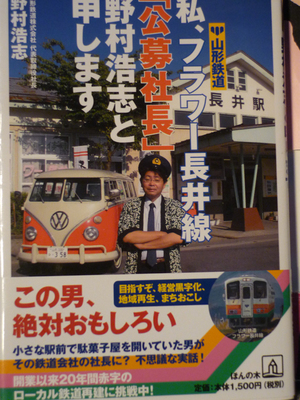



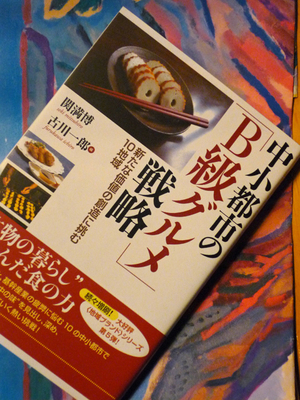


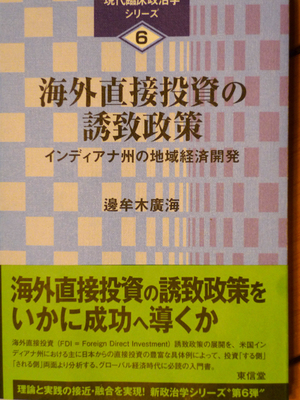

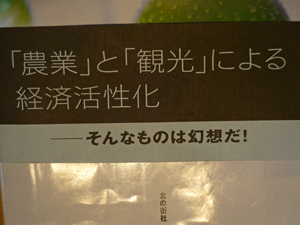

最近のコメント